Creepy Nuts「通常回」は、一見すると「日常のドラマチックさ」を歌った曲に思えるが、そのライム構造と反復技法、そして異常なまでの一貫性を保つ母音処理により、作品全体がひとつの巨大なライミング・ドキュメントとなっている。
本記事では、踏韻技法/構成/韻律設計の観点からこの作品を分解する。
🧱 フック「通常回」の“構造的韻”とリズム制御
毎日クライマックス 最終回みたいな 通常回
このラインが4小節に一度繰り返される設計は、単なるサビという枠を超えて、全体の構造を韻的にロックする錨として機能している。
- 「クライマックス(/a i a u a k s/)」
- 「最終回(/a i u a i/)」
- 「通常回(/u ー o ー a i/)」
すべてに“アイ”系二重母音の反復が含まれ、かつ三拍〜四拍の揺らぎを持つリズムラインが反復することで、異なるテーマが交差しても「リズム的帰結」が得られるようになっている。
🎢 第一連:母音設計による“連続跳躍型”脚韻群
人生変えたんは あの日フラッと入った 牛丼屋
有線で流れた衝撃 即走った TSUTAYA
J-RAPコーナー 棚にズラリ並んだ スーパースター
アンタらのおかげ 狂った14歳
このパートは、ア音(A母音)を軸にしたライム接続が主軸であるが、注目すべきは単純な母音一致ではない。
⬛ 観察点:
- 「牛丼屋 / TSUTAYA / スーパースター」:すべて語尾アクセントが上昇音調
- 母音の順序:U → A → A → A/A I/A A
- 各ラインの語尾3音に母音Aが2回以上出現
つまり、「単語の末尾だけでなく、“全体の響き”で脚韻を構成」しているという点で、クラシックなA-A-A-A形式の“尾韻主義”ではない。
これは“浮遊型母音群”とも言える、ラップにおける音楽的脚韻構成の最先端である。
📐 垂直ライムと水平ライムの交差:2連目以降の設計力
吐いて捨てるバース 道標に登った急勾配
使えないあの輪っか 俺コーラで お前はウーロンハイ
ひねくれたイズム育んだ旧校舎
ハイスピードな毎日 俺を乗せて走った9号車
この4ラインには、脚韻の多重設計が施されている。
- 「急勾配」「ウーロンハイ」:A-B脚韻(母音:/u o a i/)
- 「旧校舎」「9号車」:語尾子音+母音の連動による構造的トリプルライム
特筆すべきは、「走った9号車」のように本来ライムになりづらい数字や固有名詞を、韻として“引きずり込む”設計が行われている点。
これは意味よりも音を優先するライム理論の高度な応用といえる。
🛠「無韻」箇所の配置とフックへの収束
全編を通じて、意図的にライム密度を落とすライン(例:
ばーちゃん見送ったその足で生放送オールナイト)
が数行存在する。
しかし、これらも「サラッと逝きたいかも最終回」によって、“通常回”の反復が空白を補完する構造となっている。
つまり、「通常回」の反復は単なるキャッチーなフレーズではなく、ラップ構造上の“補完機能”を果たす設計である。
🌏 グローバル地名と即物的描写の韻処理
台中の夜市 チョイスミスって微妙な魯肉飯
リベンジ鼎泰豊 ん?これ東京にもあるのかい…
LAの夕陽 ベニスビーチ スケートパークの前
このセクションでは、地名・食・日常描写といった韻になりにくい単語を“意味のグルーヴ”で接続している。
- 「魯肉飯/あるのかい/スケートパークの前」
→ 語尾の母音:/a n/a i/a e/ → 音的には遠いが、“ゆるい母音遷移”でリズムを保つ
また、「鼎泰豊」などの日常語×固有名詞を自然にライム内に織り込むのは、R-指定が日本語ラップで育んだ“母語滑走力”のなせる技である。
🧠 押韻の先にある“意味の重層構造”
最終ブロックでは、韻が持つ機能が感情的回収の手段に進化していく。
Ain’t no 流行歌 Ain’t no 宗教家
ただ1人のラッパー 音の上にずっと居たい
ここでは英語と日本語を跨ぎながらも、「宗教家/居たい」が無理なく韻律を担保し、かつラッパーとしての矜持がテーマ的に結実している。
最後のライン:
手に汗を握る出番の10秒前
は、それまでの「通常回」のリフレインと対照的な緊張感を内包した締めであり、リズム/感情/意味の三層を締めくくる絶妙なラインである。
🔚 総評:通常回は「構造的ライムの教科書」
Creepy Nuts「通常回」は、表面的には「日常と非日常の境界」を軽妙に描いたリリックであるが、
その裏には日本語ラップの限界を突破する構造的ライム、母音設計、音韻バランス、意味との結節点が縦横無尽に仕込まれている。
これは単なる名曲ではなく、“構造をもって韻を操ること”の極致といえるだろう。
📝 この考察に対する意見や、他の曲で取り上げてほしい楽曲があればぜひコメントを!

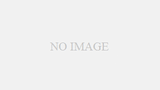
コメント