Creepy Nutsの「first penguin」は、氷上から海へ最初に飛び込むペンギンを意味する比喩を、HIPHOPシーンでのリスクを恐れず先陣を切る姿勢に重ねた一曲です。韻や語感を巧みに操りながら、挑戦、孤独、仲間との信頼を描いています。
🎤 1. タイトルとコンセプトの韻的インパクト
first penguin / 仲間と氷の上 / さぁ誰が飛び込める?
- 「first penguin」というタイトル自体がコンセプトワードで、サビに何度も登場。
- 毎回ほぼ同じフレーズで反復されるため、印象の定着とリズム感の強化を両立しています。
🎤 2. 英語と日本語のシームレスな接続
first penguin / 偉大なる一羽目 / 水面にシャチの群れ / シカトでカチこめ Who’s bangin’?
- 「first penguin」「Who’s bangin’?」のように英語を要所で挿入し、韻脚のアクセントをつくっています。
- 「一羽目」と「群れ」「カチこめ」という語尾の母音の響きが近く、内的韻を生み出しています。
🎤 3. 内韻と多音節韻の連鎖
例:
「お前らじゃ無理やで」 / 「一昨日来やがれ」 / 「その羽じゃ飛べません」U hate me?
- 「無理やで」「来やがれ」「飛べません」で母音“え”が揃い、自然な母音韻を形成。
- 連続で畳みかけることで、会話調のテンポ感が際立ちます。
🎤 4. 固有名詞とカルチャー参照のリズム効果
ティム・バートン / オズワルド・コブルポット
- 映画やキャラクター名を直接登場させ、音のユニークさとイメージの喚起力を両立。
- 「バートン」→「コブルポット」で子音の切れ味とリズムを意識。
🎤 5. 繰り返し構造による高揚感
Let’s do it do it again / Let’s do it do it again again again…
- 同じフレーズを音の粒感を変えながら反復し、ライブ映えする高揚感を演出。
- ラップバトル的な「何度でも挑む」精神を体感的に伝えます。
🎤 6. 地名・ローカルワードの配置
曽根崎 お初天神
- 大阪の具体的な地名を織り込み、ストリートのリアリティを強化。
- 日本語の固有名詞は韻的にも耳に残りやすく、地元性を象徴します。
🪶 まとめ
「first penguin」は、仲間を背負って最初に飛び込む者の覚悟を、氷上のペンギンになぞらえたリリックです。英語と日本語の織り交ぜ、固有名詞の響き、反復構造によって、曲全体が決意と昂揚感で満ちています。韻の構築はシンプルながら力強く、Creepy Nutsのストレートなメッセージ性が際立つ一曲です。

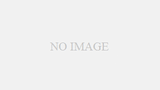
コメント